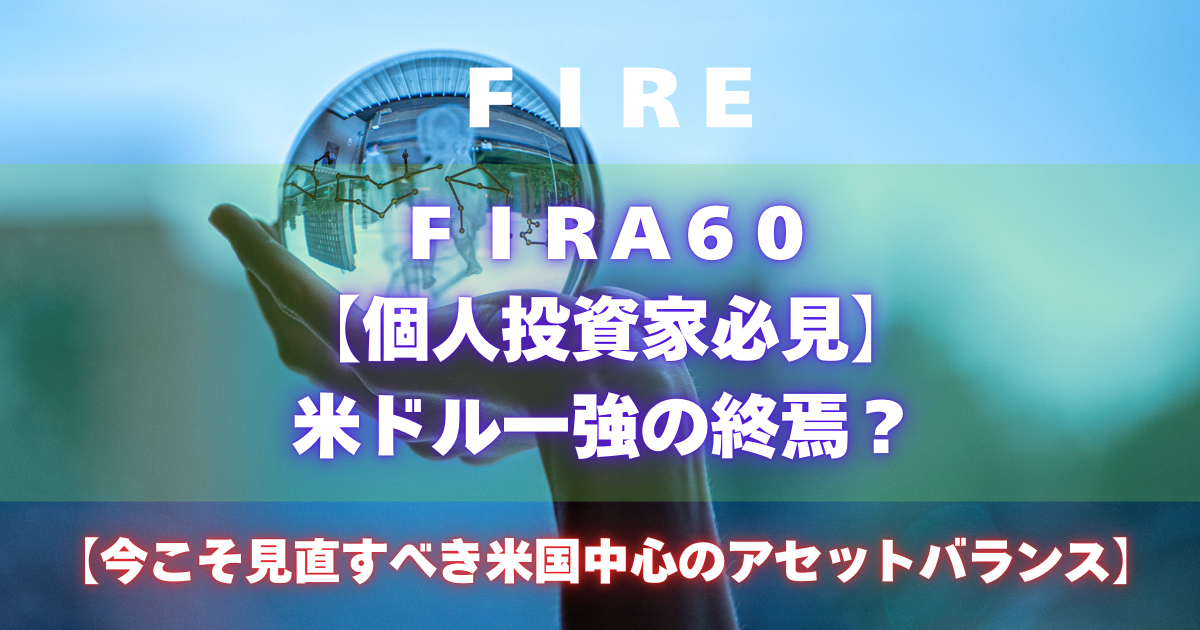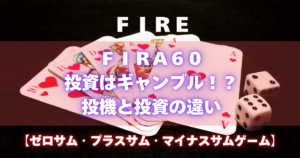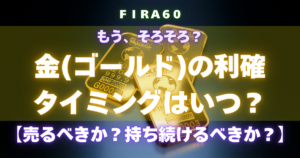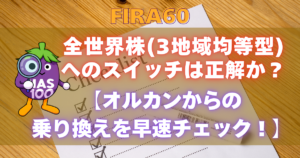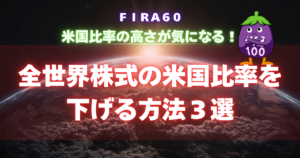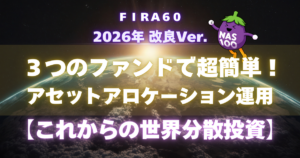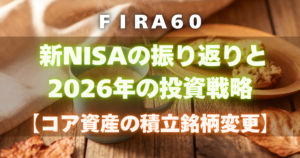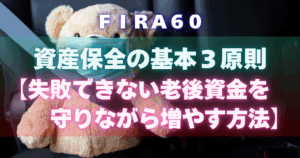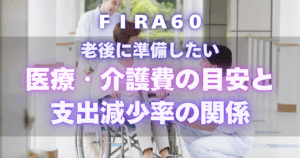長年、世界経済の中心に君臨してきた米ドルの信頼が揺らぎ、直近、基軸通貨としての地位が脅かされようとしています。
特に、米国の保護主義的な関税政策とそれに伴う金利上昇をきっかけとしてついに、グローバルな経済秩序と通貨システムに与える影響が無視出来ない状況となってきました。
このような現状を踏まえて私たちはどのように対処すれば良いのか、資産保全の観点からどのような未来を予見することができるのかについて深掘りしていきます。
本記事をご一読いただくことで、オルカン派の皆様も含め、多数派の投資方針となっている「米国中心のアセットバランス」を継続すべきかどうかについてご理解いただけます。
基軸通貨の喪失【米ドルは信頼を失うのか】米国の関税政策と金利上昇が招くドル離れの危機
以前「金(ゴールド)が重要なのか【現金では資産保全できない】」で触れましたが、世界最大級のヘッジファンド、ブリッジウォーターの創業者レイ・ダリオ氏が提唱されている「典型的なビッグサイクル」の「衰退期」が進行し、全18段階のうち、16段階目となる「基軸通貨の喪失」という危機的な状況が現実味を帯びてきました。
多くのニュース記事では、米国の保護主義的な関税政策が米国、また世界経済の景気後退を招くといったような論調で取り扱われています。
しかし、これはあくまで表向きの情報に過ぎず、レイ・ダリオ氏によると「もっと重要な経済の根幹が揺るがされている別次元の危機的状況」であるとの警鐘を鳴らしておられます。
詳しくは、こちらのグローバルマクロ・リサーチ・インスティテュートの記事をご一読ください。
2025年4月14日「レイ・ダリオ氏: 株価暴落で米国債からゴールドに資金が逃避している」
2025年4月16日「株式市場暴落、トランプ政権はこれから何度でも米国債下落に脅され続ける」
今更聞けない?基軸通貨とは?:基軸通貨が現在米ドルである主な理由

「基軸通貨の喪失」がなぜ危機的な状況となるのかについてご理解いただくために、まずはおさらいを兼ねて米ドルが「基軸通貨」となった歴史を紐解きながらお伝えします。
第二次世界大戦後のブレトンウッズ体制
1944年のブレトンウッズ協定により、米ドルは金と固定相場となり、金との交換が保証されていました(いわゆる金本位制)。
そして、他の主要通貨は米ドルに連動する体制が確立されました。これにより、米ドルは国際取引や決済の中心的な役割を担うようになりました。
しかし、1960年代に入ると、ベトナム戦争の戦費拡大と社会福祉政策の拡大により、米国の財政赤字が膨らみました。
この結果、米国の国際収支が悪化し、さらにインフレへの懸念からドルの信頼性が低下したことで他国が米ドルから金への交換を求め出し、米国の金準備が著しく減少していくことになりました。
このように米国は、金の保有量が大幅に減少する中で、破綻を防止するために1971年、リチャード・ニクソン大統領は米ドルと金の交換を停止する決断を下しました。
このニクソン・ショックと呼ばれる発表により、事実上金本位制が終了し、米ドルは金との固定相場制を離れ変動為替相場制へと移行しました。
これにより、ブレトンウッズ体制は事実上崩壊し、金本位制は終焉を迎えました。
その後、金本位制が終了した後も米ドルは広く使用され続けています。これは米国の経済力、安定した政治基盤、そして世界的な貿易取引(特に石油取引)が米ドルで行われることに大きく起因しています。また、米国の強大な軍事力と国際的な政治的影響力も、米ドルの地位を間接的に支えて来ました。



つまり、金本位制が終焉を迎えても「米国への信用が継続」したことで米ドルが基軸通貨として君臨できていたということです。
米国の関税政策が引き起こす連鎖反応:インフレと金利上昇が資産価値を蝕む
既に周知のとおり、米国は国内産業保護のため、輸入に関税を課す政策を積極的に進めています。
これは、米国の財政難解消のためとは言え、輸入品の価格上昇を通じて米国内のインフレ圧力を更に高める要因となり得ます。
ひいては、米国への投資妙味が減少することに繋がります。
輸入コストの増加と物価上昇:購買力低下の現実
関税は輸入業者にとってコスト増となり、そのコストは最終的に製品価格に転嫁され、消費者が負担する物価水準を押し上げます。
広範囲な品目にわたる関税は、インフレを深刻化させ、資産の実質的な価値、つまり購買力を低下させることに繋がります。
金融引き締めという防波堤:しかし副作用も
高まるインフレを抑えるため、米連邦準備制度理事会(FRB)は金融引き締め政策、特に政策金利の引き上げを行います。
金利上昇は、企業の借入コストが増えることを意味し、投資意欲を減退させる可能性があります。



また、住宅ローン金利の上昇は不動産市場にも悪影響を与え、個人の資産形成に暗雲を投げかけます。
米国金利上昇の波及:世界経済の不安定化と米ドル離れの足音
米国の金利上昇は世界経済にも大きな影響を与えます。
米ドル建ての債務を抱える国や企業は返済負担が増加し、経済危機のリスクが高まります。
また、新興国からの資金流出を招き、通貨安や経済成長の鈍化を引き起こす可能性も否定できません。



さらに、米国の金利上昇は一見ドル建て資産の魅力を高めるように見えますが、その裏では米ドルへの信頼を揺るがし「米ドル離れ」を加速させる要因となる可能性があります。
米ドル建て資産の魅力低下:高金利の罠
短期的に見れば米国高金利は米ドル建て資産の利回りを高めますが、それが長期化すれば景気後退のリスクが高まり、かえってドル建て資産の価値を下げる可能性があります。



他国が自国通貨を守るために金利を引き上げれば米ドル建て資産の相対的な魅力は薄れてしまいます。
関税政策による貿易摩擦:米ドルの国際的地位を揺るがす
米国の関税政策は、貿易相手国との摩擦を生み、世界的な貿易秩序を混乱させる可能性があります。報復関税の応酬は、グローバルサプライチェーンの再編を促し、米ドル以外の通貨による貿易決済の動きを加速させることにつながります。



自国中心主義的な政策は米ドルの国際的な信頼を損ない、基軸通貨としての地位を低下させる要因となり得ます。
債務上限問題と財政赤字:米ドルの信認リスクという構造的な爆弾
米国の債務上限問題や巨額の財政赤字は、長年にわたり米ドルの信認リスクを高める構造的な問題です。
政府債務の増大は、将来的なインフレ懸念や財政破綻のリスクを高め、投資家が米ドル建て資産を避ける理由となり得ます。
繰り返される債務上限を巡る政治的な混乱は、米ドルの安定性に対する疑念を増幅させます。
アレコレややこし過ぎる


新たな潮流:デジタル通貨と分散型金融が描く未来