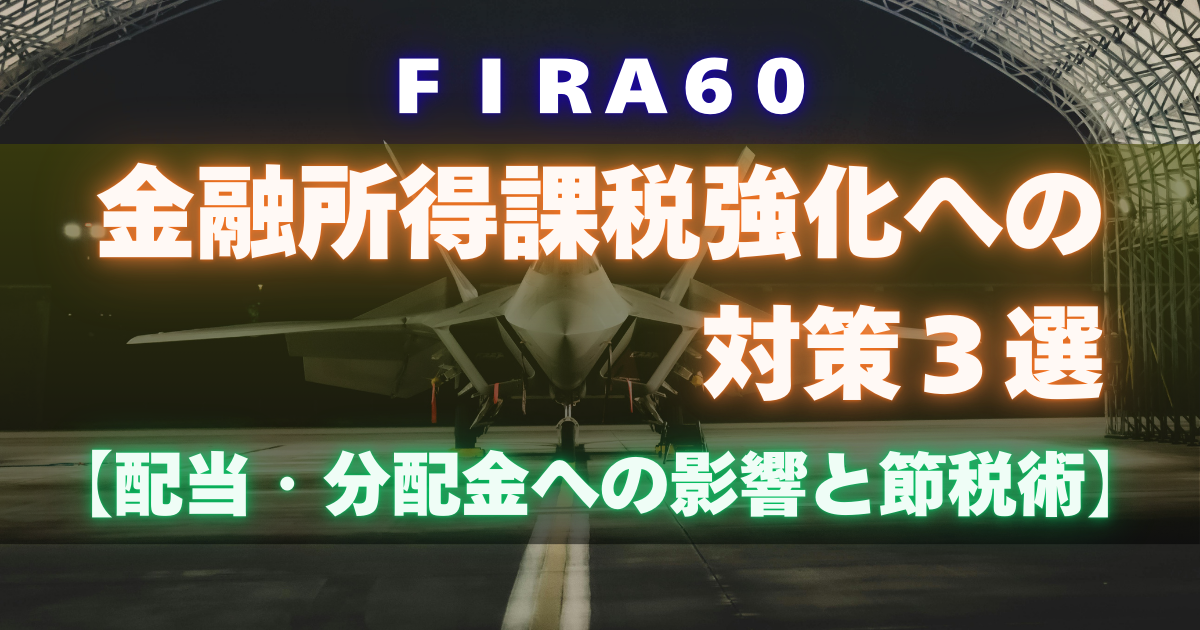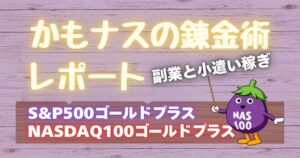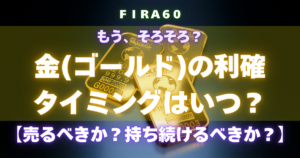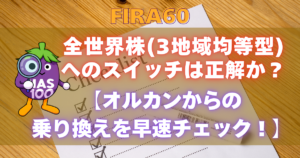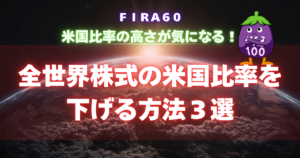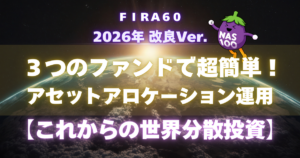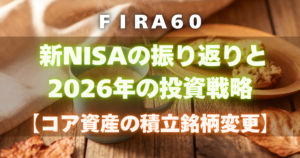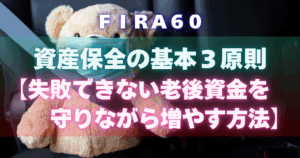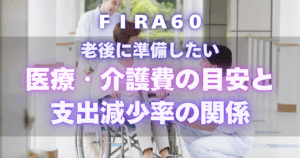FIREのうち日本の社会保障制度や退職金制度と親和性が高く、現実的に取り組みやすい点から注目を集めている早期リタイアのFIRA60。
このFIRA60を目指すうえで重要なテーマのひとつが「税金対策」です。
特に近年議論されているのが、金融所得課税の強化。
政府はこれまで優遇されてきた金融所得に対し、国民健康保険料や介護保険料といった社会保険料の算定対象に組み込むことを検討しています。
この記事では、現状の課税ルールを整理しつつ、FIRA60を目指す私たちが今からできる3つの対策を解説します。
金融所得課税の現状と今後の動向
現在の仕組み
株式や投資信託などから得られる配当金や売却益は、通常申告分離課税として「20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)」が自動的に源泉徴収されます。

特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、確定申告をせずとも課税が完了する仕組みです。
大きなメリットは、これらの所得が「社会保険料の算定基準となる所得」に含まれないこと。



つまり、仮に配当収入が数百万円あったとしても、国民健康保険料や介護保険料には影響しない仕組みとなっています。
強化の方向性



しかし、この「社会保険料への影響がない」という点が不公平であるとの議論が出ています。



労働所得や事業所得に比べて金融所得が優遇されすぎているのではないか、という考え方です。
政府内では、金融所得も国民健康保険料や介護保険料の算定基準に加える案が浮上しており、今後は投資家にとって負担が増す可能性があります。



つまり、FIRA60を目指す人にとっては、資産形成だけでなく「税と社会保険料をどうコントロールするか」が、より重要な課題となってくるのです。
今できる金融所得課税強化への対策3選



ここからは、FIRA60を目指す投資家が、今から取り組める3つの具体的な対策をご紹介します。
1. 特定口座での運用は「配当金・分配金を避ける」
特定口座で株式や投資信託を運用している場合、課税が行われるのは配当や分配金を受け取ったときと売却益が出たときです。(NISA口座は非課税)
もし今後、金融所得が社会保険料算定の対象に含まれるようになると、配当金や分配金を受け取るたびに「すべてが収入」とみなされ、国民健康保険料や介護保険料が上がる可能性があります。
ここで押さえておくべき重要なことは、資産売却で得た利益(売却益)との扱いの違いです。売却益を受け取る場合、元本には課税されず、「利益部分のみが収入」とみなされ国民健康保険料や介護保険料が上がる可能性を最小限に抑えられ、「税の繰延効果」が得られるという点です。



したがって、対策の一つは配当金や分配金を極力出さない商品を選ぶことです。
- 配当を出さない「無分配型投資信託」
- 再投資型のETF
- インデックスファンド中心の運用



こうした商品を中心にすれば、受け取る収入を抑えつつ、内部で資産を増やすことができます。
2. 特定口座は「自動取崩し」でコントロール
FIRA60を目指す段階では、資産を「積み立てるフェーズ」ですが、FIRA60を達成した後のリタイア生活においては「取り崩すフェーズ」に移っていきます。



これは、毎月一定額を売却して生活費に充てる仕組みで、定率または定額での取崩しが可能です。



なぜこれが有利なのかというと、
- 必要な金額だけを計画的に取り崩せる
- 売却益が課税対象となるが、取り崩す額を調整することで所得をコントロールできる
- 配当のように強制的に収入が発生しない
つまり、配当金のように「勝手に振り込まれて社会保険料が増える」リスクを避けながら、自分のライフプランに応じた柔軟な資金管理ができるのです。



取崩し方次第で課税額をコントロールできる点は、FIRA60達成後の出口戦略において生活の安定に大きく寄与します。
3. マイクロ法人を活用した社会保険料対策



さらに一歩踏み込んだ対策が「マイクロ法人」の活用です。
マイクロ法人とは、基本的に自分ひとりだけで設立する小さな会社のこと。



これを活用することで、次のようなメリットがあります。
社会保険料の最適化
法人からの役員報酬を最小限に設定することで、健康保険料を抑えられる。
経費計上の柔軟性
事業に関わる支出を経費として計上でき、課税所得を抑えられる。
法人税率の活用
個人よりも有利な法人税率を適用できるケースもある。
税率は原則として23.2%(2025年9月現在)ですが、所得金額のうち800万円以下の部分は15%に軽減されます(本則は19%)。



もちろん、法人設立にはコストや手間がかかります。



しかし、ある程度の金融資産を持ち、投資を事業的に運用したいと考える人にとっては有効な手段となり得ます。
特にFIRA60を目指す層にとっては、年金や退職金と合わせて「法人を使った資産管理」を組み合わせることで、税・社会保険料負担を大幅にコントロールできる可能性があります。
まとめ|課税強化を恐れるより、今できる準備を
金融所得課税の強化は、今後避けられない流れといえるかもしれません。
そして恐らく「住民税非課税戦略」などへの影響も、避けられないことでしょう。
しかし、制度が変わる前から準備をしておくことで、影響を最小限に抑えることができます。



改めて、今できる対策を整理すると以下の3つです。
- 特定口座では「配当・分配金を避ける」
- 「自動取崩し」で課税額をコントロール
- 「マイクロ法人」で資産運用の幅を広げる



FIRA60は「資産形成」だけでなく「資産を守る工夫」も同じくらい重要です。
これから数年先、制度改正が進んでも慌てないよう、今のうちから一歩ずつ備えていきましょう。
本日は、最後までお読みいただき
誠にありがとうございました。